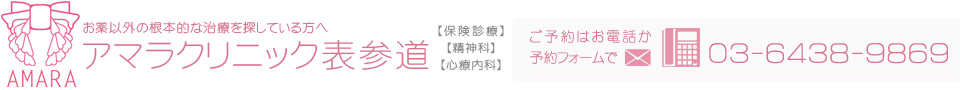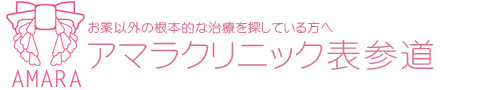うつ病の相談・治療
うつ病とは
 私たちは、生活のなかのさまざまな出来事が原因で気持ちが落ち込んだり、憂うつな気分になったりすることがあります。しかしながら人には数日もすると落ち込みや憂うつな気分から回復して、また元気にがんばろうと思える力をもっています。
私たちは、生活のなかのさまざまな出来事が原因で気持ちが落ち込んだり、憂うつな気分になったりすることがあります。しかしながら人には数日もすると落ち込みや憂うつな気分から回復して、また元気にがんばろうと思える力をもっています。ところが時に、原因が解決しても1日中気持ちが落ち込んだままで、いつまでたっても気分が回復せず、強い憂うつ感が長く続く場合があります。ブルーな気分(憂鬱な気分)がなかなか晴れず、まるでブレーキがかかったように何かをやろうという意欲が湧いてこない、この状態を抑うつ状態といいます。
具体的な症状としては、以下のようなものがあります。
- 早く目覚めて、その後眠れない
- 食欲がない
- ちょっと何かすると疲れる
- 会社に行けない
- 人と会いたくない
- 集中力が下がった
- 自信がなくなった
- 楽しめない
- 寝付けない
- 悲しい
うつ病は治療により回復します。
 「うつ病」は、現代では特別な病気ではなく、誰でもかかる可能性のある、ごく一般的な病気でもあります。
「うつ病」は、現代では特別な病気ではなく、誰でもかかる可能性のある、ごく一般的な病気でもあります。厚生労働省によると、日本人の約15人に1人が「うつ病」にかかった経験があると言われており、決して珍しい病気ではありません。しかしながら、「気の持ちようで治るはず」と自分が病気であることに気付かなかったり、「精神科にかかるのは恥ずかしい」と治療を受けないまま放置している方が多かったりすることも事実です。
うつの苦しみが続くと、症状がひどくなり、自殺の衝動にかられてしまうこともあるかもしれません。そうなる前に早期の専門的な治療を受けることが必要です。
当院での治療方針について
うつ病は基本的に適切な治療と休養で治ります(回復できます)。心理療法、休養を組み合わせつつ、回復を支えていきます。
ストレスの悩み
ストレスとは
 ストレスとは外的要因による有害刺激(ストレッサー)によって引き起こされる生理的・心理的歪みと言われています。
ストレスとは外的要因による有害刺激(ストレッサー)によって引き起こされる生理的・心理的歪みと言われています。このストレッサーに対して人は防衛反応を示して、心身のバランスを保とうとします。しかし、ストレッサーが過剰であったり長時間・長期に及ぶ場合には境界を越えて様々な心身の不調を招くことになります。
ストレスを感じたら
ある出来事がストレスになるかどうかは、その人の自我の状態(知覚・思考・行動の総体)との「かね合い」によります。
境界を越えて病気になってしまってからでは回復に時間もかかる場合もあります。当クリニックでは、ストレスの症状が軽いうちに対処し、患者さんと共にストレスへの対処の仕方を考えいていくことを行っております。心理テスト、交流分析はもちろん、なによりもお話を聞くことを通して患者さんにより良い日常生活を取り戻していただくお手伝いをさせていただきます。
境界を越えて病気になってしまってからでは回復に時間もかかる場合もあります。当クリニックでは、ストレスの症状が軽いうちに対処し、患者さんと共にストレスへの対処の仕方を考えいていくことを行っております。心理テスト、交流分析はもちろん、なによりもお話を聞くことを通して患者さんにより良い日常生活を取り戻していただくお手伝いをさせていただきます。
適応障害
適応障害とその症状
 適応障害とは、学校や会社、家庭などの身の回りの環境にうまく適応することができず、社会生活上のストレスに対する反応が、一般の人が感じる以上に強く現われ、仕事上、学業上、家庭内の生活に障をきたしてしまう症状のことを言います。
適応障害とは、学校や会社、家庭などの身の回りの環境にうまく適応することができず、社会生活上のストレスに対する反応が、一般の人が感じる以上に強く現われ、仕事上、学業上、家庭内の生活に障をきたしてしまう症状のことを言います。だれでも辛い出来事や思いどおりにならないこと(社会生活上のストレス)によって、不安やイライラが強くなったり(不安感)、悲しみや憂うつになったり(憂うつ感)、時に投げ出したくなったり、自棄になったり(逸脱行動)することは、経験したことがあると思います。
つまり、適応障害は、社会生活において、誰でも遭遇し得るストレスによって、予想外に精神的ダメージを受けた状態と言えます。予想外に精神的ダメージを受けてしまう背景には、周囲のサポート不足や本人の精神的な弱点が関与していると考えられています。
一般的な認知度はあまり高くありませんが、うつ病とおなじくらい多く見られる病気です。
症状としては
- 不安症状を中心とする状態
不安、恐怖感、焦燥感などと、それに伴う動悸、吐き気などの身体症状 - うつ症状を中心とする状態
憂うつ、喪失感、絶望感、涙もろさなど - 問題行動を中心とする状態
勤務怠慢、過剰飲酒、ケンカ、無謀な運転などの年齢や社会的役割に不相応な行動 - 身体症状を中心とする状態
頭痛、倦怠感、腰背部痛、感冒様症状、腹痛など
適応障害の治療方法
適応障害になっている患者さんは、周りの環境やストレスに対して過剰反応を起こしているケースが多くみられます。
まずは受容、共感的態度で話しを聞き、不安、緊張、恐怖によって、一時的に機能不全に至った心の働きを支えて落ち着ける必要があります。その中で、適応障害を引 き起こしているストレスを同定し、ストレスの内容が本人に対してどのような意味を持つかを理解していきます。その上で、どの様な方法で患者様がストレスに適応できるようになるかを検討します。
そしてその過剰反応を改善するために、認知行動療法など、考え方やものの見かた(認知のゆがみ)を変えるための方法を用いて治療を行っていきます。また、精神的・身体的な症状を抑えるために薬をお出しします。
まずは受容、共感的態度で話しを聞き、不安、緊張、恐怖によって、一時的に機能不全に至った心の働きを支えて落ち着ける必要があります。その中で、適応障害を引 き起こしているストレスを同定し、ストレスの内容が本人に対してどのような意味を持つかを理解していきます。その上で、どの様な方法で患者様がストレスに適応できるようになるかを検討します。
そしてその過剰反応を改善するために、認知行動療法など、考え方やものの見かた(認知のゆがみ)を変えるための方法を用いて治療を行っていきます。また、精神的・身体的な症状を抑えるために薬をお出しします。
自律神経失調症
自律神経失調症とその症状
 自律神経は体温の調節や脈拍数の調節など体の調子を整える役割を果たしています。そして、自律神経失調症とは不規則な生活や習慣などにより、身体を働かせる自律神経のバランスが乱れるためにおこる様々な身体の不調のことです。
自律神経は体温の調節や脈拍数の調節など体の調子を整える役割を果たしています。そして、自律神経失調症とは不規則な生活や習慣などにより、身体を働かせる自律神経のバランスが乱れるためにおこる様々な身体の不調のことです。症状としては体の一部が痛くなったり具合が悪くなったり精神的に落ち込んだり・・と人によって様々で、いくつか重なって症状があらわれたり症状が出たり消えたりする場合もあります。
多くみられる症状には、めまい、ふらつき、動悸、息切れ、倦怠感、疲れやすいこと、手足の冷え、発汗、頭ののぼせ、頭痛、頭重感、不眠、食欲不振などがあります。
また、病気に対する不安や心配で精神的にも不安定になっており、不安、緊張、いらいら、抑うつなどを伴うことがあります。
自律神失調症の治療
生活のリズム、食事、睡眠、運動、心にゆとりを持つ、ストレス耐性の強化、感情処理・・・など
- 自己管理によるライフスタイルの見直し
- 自律訓練法などによるセルフコントロール
- カウンセリングなどの心理療法
- 指圧やマッサージ、整体、鍼灸、ストレッチなどの理学療法
パニック障害
パニック障害とは
 パニック障害は、ある日突然、めまい、動悸、呼吸困難のような症状とともに激しい不安が発作的に起こる病気です。具体的には、満員電車などの人が混雑している閉鎖的な狭い空間、車道や広場などを歩行中に突然、強いストレスを覚え、動悸、息切れ、めまいなどの自律神経症状と「倒れて死ぬのではないか?」という強烈な不安感に襲われます。
パニック障害は、ある日突然、めまい、動悸、呼吸困難のような症状とともに激しい不安が発作的に起こる病気です。具体的には、満員電車などの人が混雑している閉鎖的な狭い空間、車道や広場などを歩行中に突然、強いストレスを覚え、動悸、息切れ、めまいなどの自律神経症状と「倒れて死ぬのではないか?」という強烈な不安感に襲われます。また、突然生じる発作が繰り返されるため、「また発作が起きたらどうしよう」という予期不安が生じるのもパニック障害の特徴で次第に一人で外出することが出来なくることもあります。
当院のパニック障害の治療
パニック障害は、「甘え」や「気持ちのゆるみ」などのために生じるものではありません。パニック障害は「脳の病気」であり適切に治療をする必要があります。
パニック障害の治療はカウンセリング・行動療法・認知行動療法などの精神療法があり、症状に応じた最適な治療を行っています。
パニック障害の治療はカウンセリング・行動療法・認知行動療法などの精神療法があり、症状に応じた最適な治療を行っています。
社会不安障害(SAD)
社会不安障害(SAD)とは
 社交不安障害(SAD:Social Anxiety Disorder)とは、人前での言動や、社交的な場での対人交流に、また、ときに人前にただいることだけにさえも強い緊張と苦痛を感じてしまう病気のことです。
社交不安障害(SAD:Social Anxiety Disorder)とは、人前での言動や、社交的な場での対人交流に、また、ときに人前にただいることだけにさえも強い緊張と苦痛を感じてしまう病気のことです。「人と接する場面で、注目されたり、恥をかいたりするのではないかととても不安になる」
「人前で発表する時にひどく緊張して動悸がしたり、顔が赤くなったり、大量に汗をかいてしまう」
「会議や会話をしている時に遠慮してしまって自分の意見が言えず、自己主張が出来ない」
大勢の人が見ている前で何かをする、初対面の人に会うというのは誰でも緊張したり不安を感じたりするものです。
しかし、その緊張や不安が強すぎるために、このような社会的状況や行為の際に生じる不安や緊張とそれにともなって現れる身体の症状が、会話や発表、発言に支障をきたすほど著しく、その苦痛から社会的状況や人前での行為を避けたくなってしまい、その結果、社会生活に障害がでてしまう状態が社会不安障害です。
人と接する場面を避けるようになったり、仕事の範囲が狭まったりと社会生活や仕事に支障を生じているなら、それは社交不安障害の可能性があります。
これまで対人恐怖症、あがり症、赤面恐怖症と呼ばれていたものもこの障害に含まれます。
社会不安障害(SAD)の症状
よく知らない人と会ったり、注目されるような発表や発言を求められたりするなどの社会的状況、人前での電話をかけたり、食事や字を書いたりするなどの社会的行為に対して強い恐怖をいだきます。
また恐怖にともなって、緊張・赤面・発汗・ふるえ・動悸・声がでない・息苦しさ・腹痛・尿意頻回・ぎこちない行動など身体の症状が現れるため苦痛が強く、さらに、この身体の症状が余計に周囲に「変に思われるのではないか」という不安につながり、緊張症状を強める結果となります。
具体的症状としては
また恐怖にともなって、緊張・赤面・発汗・ふるえ・動悸・声がでない・息苦しさ・腹痛・尿意頻回・ぎこちない行動など身体の症状が現れるため苦痛が強く、さらに、この身体の症状が余計に周囲に「変に思われるのではないか」という不安につながり、緊張症状を強める結果となります。
具体的症状としては
- 人前で何かを発表することに、極度に苦痛を感じる(スピーチ恐怖)
- オフィスなどで、かかってきた電話に出るのが怖い(電話恐怖)
- 人前で字を書こうとすると、手が震えてしまう
- 誰かと一緒だと食べ物が喉を通らない(外食(会食)恐怖)
- 人にみられていると思うと、何かを持った手が震えてしまう(振戦恐怖)
社会不安障害(SAD)の治療
精神療法
 患者さんご自身がなぜ不安や恐怖を感じるのかを知り、不安をコントロールしながら、これまで避けていた状況に立ち向かうことができるように訓練します。
患者さんご自身がなぜ不安や恐怖を感じるのかを知り、不安をコントロールしながら、これまで避けていた状況に立ち向かうことができるように訓練します。森田療法も有効な治療法として用いられています。治療の流れは「恥ずかしがってはならない、堂々としていなければならない」といった思い込みによって社交不安障害の症状が生じてしまう悪循環を断ち切るため、まずは自分の感情をあるがままに認め、不安や緊張する自分と向き合うことから始まります。